日本の学童保育を読ませていただき、全国様々な学童活動の詳細や、子どもの�...
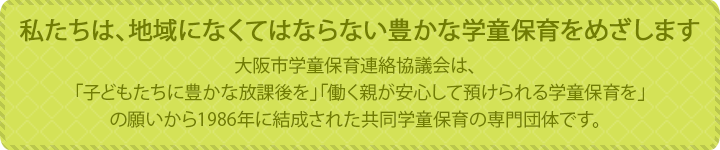
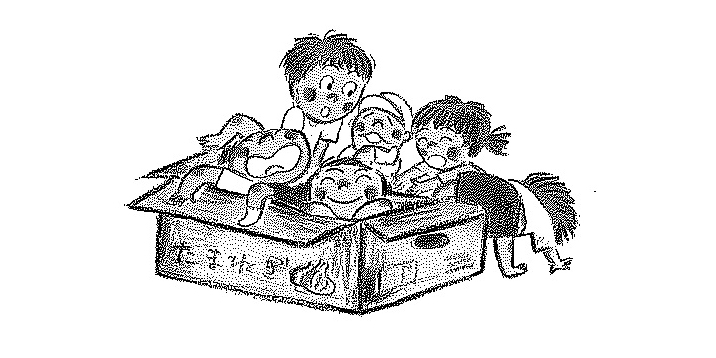
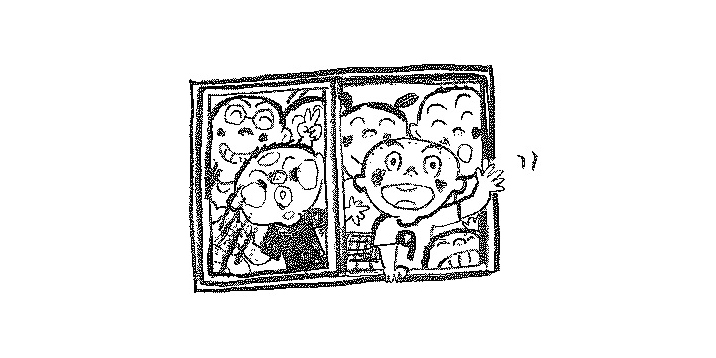

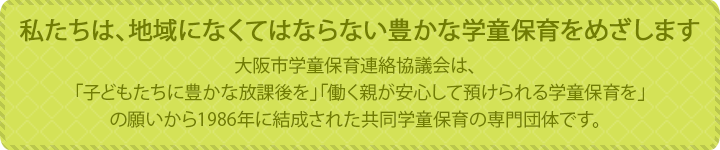
日本の学童保育を読ませていただき、全国様々な学童活動の詳細や、子どもの�...
3月の卒所式や春休みの新一年生の受け入れ、4月の申請作業、5月の行政区�...
日本の学童保育、存在は知っていたけれど、なかなか手を出すことができずで...
2月号の特集は全国研の報告です。当日の写真から会場の熱気がとても伝わりま�...
9月19日の署名スタート集会を経て、今年も子どもたちの豊かな乳幼児期・�...
7月26日、「学童保育の整備・充実を求める要望書」を大阪府に提出しました。 8...
日時:2023年9月17日(日)10:00~12:00 開催:ズームまたは会場 会場:大...
みなさまのご意見を受け、今年度よりウェブ通信を発行することになりました�...
日本の学童保育を読ませていただき、全国様々な学童活動の詳細や、子どもの教育・保育の多種多様な情報を知ることができ、とても勉強になりました。
今回その中でもジェンダーについて語られているものがあり、とても興味深く目を通させていただきました。
男性が主に外で働き、女性が家庭を守ると言うスタイルは意外にも近年構築されたもの。それが作られた時代背景や状況、それにより現在共働き家庭が増えているものの、家事や育児を主にどちらかが担う(特に女性)ワンオペの状態が問題となっていること等、学ぶことが沢山ある記事で読み応えがありました。
自分自身もジェンダー差別などないよう、平等な価値観で物事を考えれるよう子どもに教えていかねばならないと思いましたし、学童保育の中でも様々な仲間がいること、そして1人1人を尊重して育っていけるように考えて行って欲しいと思うお話でした。
保護者